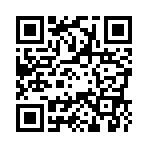★これまでの活動★ブログ内「活動記録日誌」へ(ぜひ、見てみてね♪)
★活動スケジュール★ しまだ子育てカレンダー へ(「こだわり検索」⇒りとるきっず検索)
・ ・ ・メンバー・スタッフ・見守り隊 随時募集中・ ・ ・
*「みんなの日記-shio)」は 『りとる☆ピースなshioの日記』にお引っ越ししましたm(__)m
2009年08月24日
たごっこパークへ
~shio~
8月22日(土)
やっと、来ることができました!
富士市のゆめ・まち・ねっとさん主催の「冒険遊び場たごっこパーク」

飛び込んでます、飛び込んでます!
車で 走っていて この光景が見えたときは、びっくり・・

なぜって、すぐ横の道路には 普通に車が走っているんです。

さっきまで、川で遊んでいた女の子が ずぶぬれのまま、小さい子と 遊んでいました。

近所のおじいちゃんたちも、子供たちとこの空間を共有することを、居心地良さそうにして過ごしていました。
そこには、無理している人はいない・・ まったりとした空気が漂っていました。。
せみの声が かなり大きく響いていました。

小学校高学年~中学生くらいの子たちが 遊んでいました!
飛び込んだ子供たちが 脇にかけられたはしごを伝って 上ってきます。
その顔は、なんともいえない・・子供らしい顔だと思いました。
ちい兄ちゃんが「あの子たち、着衣泳で 泳いでいるねぇ。」と言いました

蝉の抜け殻
私が見学している間、おとーさんと 集めてました。
子供たちは、ここに来るまで 道に迷ってしまったこともあり、車の中で まったり?とくつろいでいました、、
・・・・・・・・・・・・・・・・
お兄ちゃん(15歳)が 小さいときに「プレーパーク」(羽根木だったかな・・)をTVで知り、「これだ!」と思いました。
そして、ず~っと この目で見たかった「たごっこパーク」。
そこには、ほんとうに まったりとした 静かな空気が流れ、無理をしていない人たちの集まりがありました。
私は日ごろ、特に無理しているつもりはないけど、そこにいると・・私って、どっか無理してるのかな・・って感じました。
「ここでは、無理しなくていいんだな」って気持ちになりました。
「(子どもたちが 飛び込んでいる川)決して きれいな川ではないでしょ。」とミッキーさん(奥さん)。
よく「(衛生上)入らないでください」と 行政から言われないなぁ・・と、富士市の懐の深さも凄いなぁと思いました。
それも、ゆめ・まち・ねっとさんが 少しずつ積み上げてきたことが 認められているからなんでしょうね。
代表のたっちゃん&ミッキーさんが言いました。
「子供たちが大きくなったときに、ミッキー(大人)と遊んだ思い出というより、子供同士で遊んだ思い出であって欲しい」
「最初は、木に登って見せたり、ベーゴマをやってみせたりしていたけれど・・・」
・・今は、大人は本来ならいなくていい存在。存在感がなくていい。本来なら、遊びは子供だけの世界であるべきもの。さらにいえば、そういう場があるのなら、プレーパークなんてなくていい、必要ない。
それは、6年目を迎える活動から、導き出された結論なのだということ。
また、ある中学生の男の子は マンガの本を読見ながら、のんびりと談笑していた。
その子は、いつも川には入らないらしい。
普通、そのように 過ごす子がいたら、大人としては 「川のほうで皆と遊んできたら」などと 世話をやきたくなるけれど、そんなこともしない。たっちゃんは、「この子から 学ぶことが大きかった」と言っていました。
そして、帰り際に 川のところに さっきまで無かった立て札が、「幼児・小学生(低学年だったかな?)は 大人と一緒に入ってください」と書いてあった。
ふと、プレーパークって ルールがないのでは?
と思った。
聞いてみると、慣れない川で 皆が入っているから安全と思い、流されてしまうことがあるのだそう。
それを 助けるために 大人が飛び込むこともあるのだそう・・ しかし、だいたいは、慣れた子供たちが 助けてくれるらしい。
これは、大人のルールなんだな・・(大人が知っているべき危険と言った方がいいのかな?)と思った。
親の世代でさえ、「なにが危険なのか」がよく分からなくなっていると思う。
今の社会環境は、子供が遊ぶには、あまりにも「してはダメなこと」が多すぎるのかもしれないと思う。
もうひとつ、思ったこと。
肩肘はらず、空間を用意することから始めて、自分たちができることからやればいいんだな・・と思った。
8月22日(土)

やっと、来ることができました!
富士市のゆめ・まち・ねっとさん主催の「冒険遊び場たごっこパーク」

飛び込んでます、飛び込んでます!
車で 走っていて この光景が見えたときは、びっくり・・

なぜって、すぐ横の道路には 普通に車が走っているんです。

さっきまで、川で遊んでいた女の子が ずぶぬれのまま、小さい子と 遊んでいました。

近所のおじいちゃんたちも、子供たちとこの空間を共有することを、居心地良さそうにして過ごしていました。
そこには、無理している人はいない・・ まったりとした空気が漂っていました。。
せみの声が かなり大きく響いていました。

小学校高学年~中学生くらいの子たちが 遊んでいました!
飛び込んだ子供たちが 脇にかけられたはしごを伝って 上ってきます。
その顔は、なんともいえない・・子供らしい顔だと思いました。
ちい兄ちゃんが「あの子たち、着衣泳で 泳いでいるねぇ。」と言いました


蝉の抜け殻
私が見学している間、おとーさんと 集めてました。
子供たちは、ここに来るまで 道に迷ってしまったこともあり、車の中で まったり?とくつろいでいました、、

・・・・・・・・・・・・・・・・
お兄ちゃん(15歳)が 小さいときに「プレーパーク」(羽根木だったかな・・)をTVで知り、「これだ!」と思いました。
そして、ず~っと この目で見たかった「たごっこパーク」。
そこには、ほんとうに まったりとした 静かな空気が流れ、無理をしていない人たちの集まりがありました。
私は日ごろ、特に無理しているつもりはないけど、そこにいると・・私って、どっか無理してるのかな・・って感じました。
「ここでは、無理しなくていいんだな」って気持ちになりました。
「(子どもたちが 飛び込んでいる川)決して きれいな川ではないでしょ。」とミッキーさん(奥さん)。
よく「(衛生上)入らないでください」と 行政から言われないなぁ・・と、富士市の懐の深さも凄いなぁと思いました。
それも、ゆめ・まち・ねっとさんが 少しずつ積み上げてきたことが 認められているからなんでしょうね。
代表のたっちゃん&ミッキーさんが言いました。
「子供たちが大きくなったときに、ミッキー(大人)と遊んだ思い出というより、子供同士で遊んだ思い出であって欲しい」
「最初は、木に登って見せたり、ベーゴマをやってみせたりしていたけれど・・・」
・・今は、大人は本来ならいなくていい存在。存在感がなくていい。本来なら、遊びは子供だけの世界であるべきもの。さらにいえば、そういう場があるのなら、プレーパークなんてなくていい、必要ない。
それは、6年目を迎える活動から、導き出された結論なのだということ。
また、ある中学生の男の子は マンガの本を読見ながら、のんびりと談笑していた。
その子は、いつも川には入らないらしい。
普通、そのように 過ごす子がいたら、大人としては 「川のほうで皆と遊んできたら」などと 世話をやきたくなるけれど、そんなこともしない。たっちゃんは、「この子から 学ぶことが大きかった」と言っていました。
そして、帰り際に 川のところに さっきまで無かった立て札が、「幼児・小学生(低学年だったかな?)は 大人と一緒に入ってください」と書いてあった。
ふと、プレーパークって ルールがないのでは?
と思った。
聞いてみると、慣れない川で 皆が入っているから安全と思い、流されてしまうことがあるのだそう。
それを 助けるために 大人が飛び込むこともあるのだそう・・ しかし、だいたいは、慣れた子供たちが 助けてくれるらしい。
これは、大人のルールなんだな・・(大人が知っているべき危険と言った方がいいのかな?)と思った。
親の世代でさえ、「なにが危険なのか」がよく分からなくなっていると思う。
今の社会環境は、子供が遊ぶには、あまりにも「してはダメなこと」が多すぎるのかもしれないと思う。
もうひとつ、思ったこと。
肩肘はらず、空間を用意することから始めて、自分たちができることからやればいいんだな・・と思った。
Posted byりとるスタッフat17:26
Comments(4)
shio
この記事へのコメント
見学報告をありがとうございます。
無理をしない…それは現場での僕らのスタンスです。
いろんな理由があります。
僕らが肩肘張らずに過ごすことで、ボランティア的に関わってくれているお父さん、お母さん、おじいちゃんたちも自然体で子どもたちに関わってもらうための空気づくり。
大人が主役の遊び場にならないようにするための僕とみっきーの仕掛けです。
全体をいつでも視野にいれていられるようにという側面もあります。
ご覧のとおり、子どもたちははちゃめちゃに遊んでいます。川への飛び込みや火遊びなどは、危険な側面もあります。時には大人が助けに入らなきゃならない場面も生じるかもしれません。
そうしたことが、スタッフ一人ひとりが自分の持ち場があって、それを張り切ってこなしていたら、見落とす可能性が大きくなるんじゃないかと思うんです。
そのために平時にはのんびりと子どもたちを見ているということです。僕が子どもたちと一緒になって川への飛び込みをしていたら、向こうで一人、子どもが流されていたなんてことも見落としてしまいますからね。
子どもたちが僕らに関わる隙を作っていてあげるという面もあります。僕もみっきーも暇そうなので、「たっちゃん、見ててよ。」、「みっきー、聞いて、聞いて。」という子どもたちからの声が間断なく続きます。
ほら、家庭でもそうでしょ。子どもは「お母さん、見てて。でんぐり返しができるようになったよ。」とか「あのね、今日、学校でね…」なんて話しかけてきたり。それをつい、「お母さん、忙しいから、あとで」なんてことになってしまったり。
あるいは、忙しそうにしているので、「ねぇ、お母さん」なんて声を掛けることすら子どもが躊躇っていたりなんてこともあるでしょう。
子どもたちの見てて、聞いてを受けとめるために暇そうに演じているという部分もあるわけです。
そして、一人ひとりの子どもを観察し、そこから僕らが学ぶために僕らが張り切って、「子どもたちのために」なんて動き回らないという面もあります。
(あの子、あのあと、何をするんだろう)とか(おっ、あいつらケンカになりそうだな)とかも観察しているんです。
そこで子どもたちがどんな姿を見せてくれるのか。そこから学んだことを社会に届けるために、僕らは観察者になる、という感じですね。
こうしたことはあくまでも現場での僕らの過ごし方です。
ただ、現場でそうした肩肘を張らない、無理をしない動きをするためには、日ごろは相当にいろんな無理を重ねています。
最近はよく、NPOのミッションは…なんていう言い方がありますが、僕は日本語の「使命」のほうがしっくりきます。
命を使うにたる市民活動だと確信しながら、今日もみっきーと二人三脚、がんばっています。
無理をしない…それは現場での僕らのスタンスです。
いろんな理由があります。
僕らが肩肘張らずに過ごすことで、ボランティア的に関わってくれているお父さん、お母さん、おじいちゃんたちも自然体で子どもたちに関わってもらうための空気づくり。
大人が主役の遊び場にならないようにするための僕とみっきーの仕掛けです。
全体をいつでも視野にいれていられるようにという側面もあります。
ご覧のとおり、子どもたちははちゃめちゃに遊んでいます。川への飛び込みや火遊びなどは、危険な側面もあります。時には大人が助けに入らなきゃならない場面も生じるかもしれません。
そうしたことが、スタッフ一人ひとりが自分の持ち場があって、それを張り切ってこなしていたら、見落とす可能性が大きくなるんじゃないかと思うんです。
そのために平時にはのんびりと子どもたちを見ているということです。僕が子どもたちと一緒になって川への飛び込みをしていたら、向こうで一人、子どもが流されていたなんてことも見落としてしまいますからね。
子どもたちが僕らに関わる隙を作っていてあげるという面もあります。僕もみっきーも暇そうなので、「たっちゃん、見ててよ。」、「みっきー、聞いて、聞いて。」という子どもたちからの声が間断なく続きます。
ほら、家庭でもそうでしょ。子どもは「お母さん、見てて。でんぐり返しができるようになったよ。」とか「あのね、今日、学校でね…」なんて話しかけてきたり。それをつい、「お母さん、忙しいから、あとで」なんてことになってしまったり。
あるいは、忙しそうにしているので、「ねぇ、お母さん」なんて声を掛けることすら子どもが躊躇っていたりなんてこともあるでしょう。
子どもたちの見てて、聞いてを受けとめるために暇そうに演じているという部分もあるわけです。
そして、一人ひとりの子どもを観察し、そこから僕らが学ぶために僕らが張り切って、「子どもたちのために」なんて動き回らないという面もあります。
(あの子、あのあと、何をするんだろう)とか(おっ、あいつらケンカになりそうだな)とかも観察しているんです。
そこで子どもたちがどんな姿を見せてくれるのか。そこから学んだことを社会に届けるために、僕らは観察者になる、という感じですね。
こうしたことはあくまでも現場での僕らの過ごし方です。
ただ、現場でそうした肩肘を張らない、無理をしない動きをするためには、日ごろは相当にいろんな無理を重ねています。
最近はよく、NPOのミッションは…なんていう言い方がありますが、僕は日本語の「使命」のほうがしっくりきます。
命を使うにたる市民活動だと確信しながら、今日もみっきーと二人三脚、がんばっています。
Posted by たっちゃん@ゆめ・まち・ねっと at 2009年08月25日 12:28
マンガ本を読んでいた中学生について
彼は僕らの師匠の一人ですね。
もう5年の付き合いになりました。
彼は時々、ドーパミンががんがんに出て、川に入る時もあります。
廃材ですごい作品を作る時もあります。
焚き火で創作料理をする時もあります。
みんなの輪に入り、ボール遊びをする時もあります。
小さい子や泣いている子を見ると、放っておけない質なので、すぐに寄っていきます。
たごっこパーク全体が彼の居場所であり、その中にさらに自分だけの居場所をレジャーシートやベニヤ板で確保しているんでしょうね。
安心して遊べるということの本当の意味を彼から学ばせてもらっているように思います。
彼は僕らの師匠の一人ですね。
もう5年の付き合いになりました。
彼は時々、ドーパミンががんがんに出て、川に入る時もあります。
廃材ですごい作品を作る時もあります。
焚き火で創作料理をする時もあります。
みんなの輪に入り、ボール遊びをする時もあります。
小さい子や泣いている子を見ると、放っておけない質なので、すぐに寄っていきます。
たごっこパーク全体が彼の居場所であり、その中にさらに自分だけの居場所をレジャーシートやベニヤ板で確保しているんでしょうね。
安心して遊べるということの本当の意味を彼から学ばせてもらっているように思います。
Posted by たっちゃん@ゆめ・まち・ねっと at 2009年08月25日 12:39
川のところにあった看板や公園入り口に掲げてあるメッセージ看板は、書いてくださってあるとおり大人向けです。
川に書いてあるのは、危険性を大人が知っていてね、という意味合い以上に、お客さんにならないでくださいね、ということを伝えたいと思っているのです。
僕らはレジャーランドの流れるプールの監視員ではないわけです。
幼児をあの川で一人遊ばせて、「監視員さん、うちの子も見ていてくださいね。何かあったら、すぐに飛び込んで助けてくださいね。」という親御さんと私たちとの関係では、市民活動として成り立っていきませんし、まちづくりにもつながっていきません。
「子どもたちをこういう環境でこんなふうに遊ばせてあげながら育てていきたいよねぇ。」と思ってくださる大人の輪を広げていきたいわけです。
そのために、単なるサービスの受け手にならんとする親御さん向けとして川の看板だったり、募金の呼びかけであったり、片付けへの協力依頼であったりします。
そうそう、たごっこパークは10時開始なので、僕らがあの公園に到着するのも10時ぎりぎりなのです。
8時に行って準備万端、さぁ、お客さん、いらっしゃいというスタンスを取るのではなく、10時開始で、子どもたちが焚き火をやりたくなったら、マッチを準備してあげる、うちわや火バサミを出してあげる。
川で遊びたくなったら、縄梯子を出してあげる。
そうやって子どもたちと、あるいは参加している親御さんたちとその日、その日の場づくりをしています。
その積み重ねがまちづくり、地域づくりにつながり、社会を豊かにしていくんだと思うからです。
川に書いてあるのは、危険性を大人が知っていてね、という意味合い以上に、お客さんにならないでくださいね、ということを伝えたいと思っているのです。
僕らはレジャーランドの流れるプールの監視員ではないわけです。
幼児をあの川で一人遊ばせて、「監視員さん、うちの子も見ていてくださいね。何かあったら、すぐに飛び込んで助けてくださいね。」という親御さんと私たちとの関係では、市民活動として成り立っていきませんし、まちづくりにもつながっていきません。
「子どもたちをこういう環境でこんなふうに遊ばせてあげながら育てていきたいよねぇ。」と思ってくださる大人の輪を広げていきたいわけです。
そのために、単なるサービスの受け手にならんとする親御さん向けとして川の看板だったり、募金の呼びかけであったり、片付けへの協力依頼であったりします。
そうそう、たごっこパークは10時開始なので、僕らがあの公園に到着するのも10時ぎりぎりなのです。
8時に行って準備万端、さぁ、お客さん、いらっしゃいというスタンスを取るのではなく、10時開始で、子どもたちが焚き火をやりたくなったら、マッチを準備してあげる、うちわや火バサミを出してあげる。
川で遊びたくなったら、縄梯子を出してあげる。
そうやって子どもたちと、あるいは参加している親御さんたちとその日、その日の場づくりをしています。
その積み重ねがまちづくり、地域づくりにつながり、社会を豊かにしていくんだと思うからです。
Posted by たっちゃん@ゆめ・まち・ねっと at 2009年08月25日 12:56
たっちゃん@ゆめ・まち・ねっとさんへ
深い、深い・・経験からくるお話、ありがとうございます。
「無理をしない」にも、そんなにいろんな意味や理由があるのですね。無理をしないことに無理をしている・・そんなお話を聞いて、子供を自由に遊ばせるために・・命を守るための強い責任感や、根っこの本当に大事な部分を忘れない使命感をひしひしと・・強く感じます。
このような大事なお話をうかがえて、とてもありがたく思います。
今回は、短い時間立ち寄らせていただいただけでしたが、このようなお話もうかがえて、私たちにあった「居場所づくり」ができたら・・という形が見えてきたように思います。
深い、深い・・経験からくるお話、ありがとうございます。
「無理をしない」にも、そんなにいろんな意味や理由があるのですね。無理をしないことに無理をしている・・そんなお話を聞いて、子供を自由に遊ばせるために・・命を守るための強い責任感や、根っこの本当に大事な部分を忘れない使命感をひしひしと・・強く感じます。
このような大事なお話をうかがえて、とてもありがたく思います。
今回は、短い時間立ち寄らせていただいただけでしたが、このようなお話もうかがえて、私たちにあった「居場所づくり」ができたら・・という形が見えてきたように思います。
Posted by shio at 2009年08月26日 20:06
at 2009年08月26日 20:06
 at 2009年08月26日 20:06
at 2009年08月26日 20:06